「手作り醤油ってできるの?」と思っていませんか?
田舎暮らし15年、村の仲間と共に育てた発酵調味料は、
手間を楽しみに変える「村仕事」の醍醐味。
家庭でも取り入れられる発酵文化の魅力を、体験談とともにご紹介します。
**************

発酵食品を手作り、田舎暮らしを実践している椿留美子です。
東京から家族で移住、のんびり・・と思いきや、全く忙しい!
全然スローライフじゃないよ〜、と思いながらあたふたしています。
田舎暮らしの知恵と奥深さをお伝えしたいと
東京と田舎を行ったり来たりしながら発酵教室を開催しています。
村仕事から学ぶ「手作り醤油」の暮らし|発酵調味料とともに育つ田舎暮らしの醍醐味

お醤油は買うもの? 田舎で出会った「手作り醤油」という暮らし
初めての衝撃。「お醤油って作れるの?」
「お醤油を作ってるんだよ」
そんなお話を友人から聞いたのは、田舎に移住して間もない頃のことでした。
「え、お醤油を作ってるの??」
買うのが当たり前だったお醤油が、まさか自分の手で仕込めるなんて——
出会いは移住後、移住者の仲間とのつながりから
私が移住した地域には“お醤油作りグループ”が複数存在し、
それぞれが独自に「手作り醤油」に取り組んでいるのです。
私が今、参加しているのもそのひとつ。
ここでは、年に一度の仕込みから始まり、
熟成、絞り、瓶詰めまで、すべて仲間と協力して行います。
醤油樽はパン教室の隣に
お醤油樽は、なんと私のパン教室の隣に設置されています。

田舎暮らしと発酵調味料、そして人とのつながりが交差する
大切な場所です。
1年以内でできる!?絞り師が伝えた「主婦でもできる手作り醤油」の製法
1年未満で完成する醤油、その秘密は?
本物の醤油って、2年や3年かけて作るもの。
そう思っていませんか?
スーパーで手軽に手に入るものは短期間で熟成させて、大量生産しているものがほとんどです。
それに対して、昔ながらの製法で作る天然醸造のものは
何年も時間がかかる
私もそう思っていました。
でも、今作っているこの手作り醤油は——なんと、1年以内で完成するんです。
もちろん、発酵調味料としての質を落とすことなく、
しっかりと熟成され、香りも味も深い。
それが可能なのは、「絞り師」と呼ばれる職人の知恵による製法があるから。
亡き絞り師さんが遺した知恵
その方は長野県にお住まいのお醤油の絞り師さん。
地元の主婦たちでも作れるようにと、
最小限の天地返しで効率よく仕上げる手法を確立されました。
実際、私たちもあまり頻繁には混ぜ返しをしません。
なのに、美味しい!
この絞り師さんはすでに他界されていますが、
彼の知恵と技術はお弟子さんの絞り師の方が引き継がれています。

「村仕事」という文化:忙しい主婦たちが支える発酵調味料の現場
5年越しで入れたお醤油グループの世界
お醤油作りが始まったその地域では、
村単位の共同作業として取り組んでいたそうです。
なんと、テレビの地方局のドキュメンタリーでも取り上げられていました。
私たちのお醤油作りもまさにその一環。
今や全国に広がっています!
実は私は地元のこのグループに入れてもらえるまで、
5年ほどかかりました。
やりたい人が多く、空きがなかなか出ないうえ、
真剣に取り組む意志がないと受け入れてもらえなかったんです。(現在はそこまでではありません、チームの意向に沿って臨機応変になっています)
それだけ、真剣に取り組んでいる“文化”なのです。
仕込みから絞り、瓶詰めまで、年中行事のような共同作業
1年の流れはこうです。
- 春:仕込み(大豆、小麦、塩、水、醤油麹)
- 夏:発酵促進、天地返し
- 冬:絞り(「ふね」で圧をかける)
- 瓶詰めと配分
材料にもこだわっています。
1年の最大イベントである「お醤油絞り」は
長野の絞り師さんをお呼びして1日がかりで行われます。
薪で湯を沸かし、熟成されたもろみを一斗樽から絞っていきます。

そのあとは、お楽しみのランチタイム。
毎年みんなで持ち寄ったおかずにで搾りたてのお醤油をいただきます。

今回はうどん、そして新鮮な卵。
そこに出来立てのお醤油をかけていただく「卵かけうどん」は、
至福そのもの!子どもたちも「おいしい〜」と笑顔になります。

絞りの後は分配作業になります。
各自、瓶を持ち寄って詰めていきます。(瓶詰め作業と呼んでいます)
この分配作業も、信頼関係あってこそ。
ずらっと並んだ一升瓶に、各家庭の1年分を分けていきます。

“作る暮らし”の幸せ:手作り醤油がくれた10年分の気づき
醤油がつなぐ人と人、世代と季節
このお醤油作りに関わって10年。
初めての時は右も左もわからず、ただ皆さんの後ろについていくだけ。
でも今は、樽の状態やもろみの香りで「今年は良さそう」と感じるようになりました。
ふと気づけば、メンバーのお子さんたちも、当たり前のように作業に加わるようになっています。
子どもが舐めて喜ぶ「本物の味」
絞りの時、ポタポタ落ちてくるお醤油の味見をするのも
お楽しみの一つです。
「今年もお醤油、美味しいね」
そう言って子供たちもぺろぺろ舐めて味見をします。
それが手作りの醍醐味だなあ、と思っています。

自分で育てたもろみ、自分で瓶詰めしたお醤油。
その味は、ただの調味料ではなく、
手作りの記憶
仲間との絆
そして自分自身の成長そのもの
です。

もっと知りたい方へ:田舎の発酵ライフや教室案内はこちらから
私が運営している「発酵クラス」では、
このような発酵調味料の手作り体験や、田舎暮らしの知恵もシェアしています。
もっと発酵にふれてみたい方
自分の暮らしに“作る喜び”を取り入れたい方は
ぜひメルマガにご登録ください。
👉 📩 メルマガ登録はこちら
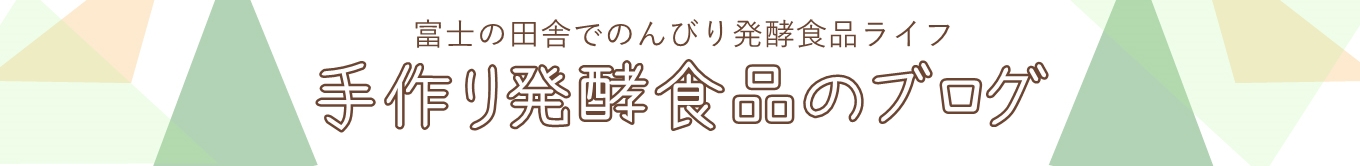

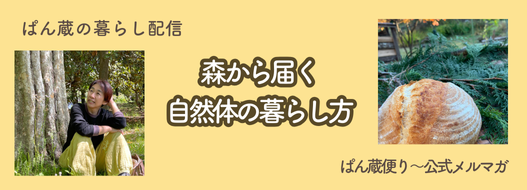
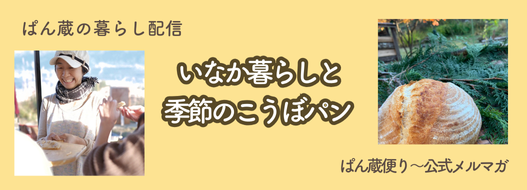


コメント