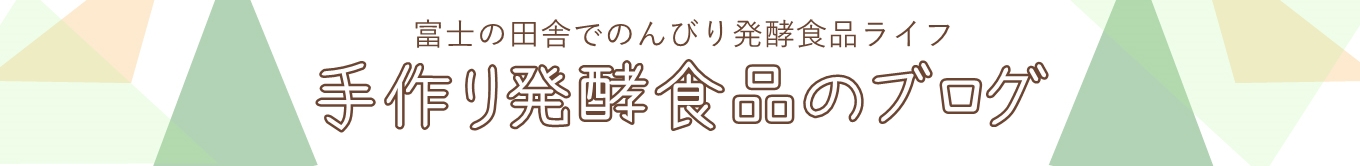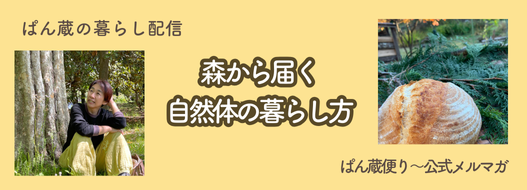ぱん蔵のレッスンには
発酵クラス
というレッスンがあります。
発酵クラスといっても単に「発酵教室」というわけではなく
発酵食品、伝統食品、保存食品などをみんなで作っていく講座で
毎月1回くらいのペースで行われています。
今日は
「なぜ発酵教室をやろうと思ったか」
というお話をしようと思います。
**************

発酵食品を手作り、田舎暮らしを実践している椿留美子です。
東京から家族で移住、のんびり・・と思いきや、全く忙しい!
全然スローライフじゃないよ〜、と思いながらあたふたしています。
田舎暮らしの知恵と奥深さをお伝えしたいと
東京と田舎を行ったり来たりしながら発酵教室を開催しています。
発酵教室 – 近所のおばあちゃんたちがすごい〜発酵教室を始めた訳
ぱん蔵のうちの周りにはおじいちゃん、おばあちゃんたちお年寄りが多いです。
どっちかっていうとおばあちゃんが多いかな。
70代はもちろん、80代、90代の方も現役で畑仕事をしてらっしゃいます。
若者に負けないくらい本当にお元気です。
手作りこんにゃくに感動
ある時に手作りのこんにゃくをいただいて
「こんにゃくって作れるの??」
ということがありました。
.jpg)
地域のお祭りで手作りこんにゃくを売っていたりもします。
こんにゃく芋からこんにゃくを作るというのを知ったのもそれがきっかけです。
市販で売られているものはこんにゃく粉を使っていて、芋からではなかったんですね。
こんにゃく粉から作ったものと、こんにゃく芋から作ったものとでは
食感が全然違う!
そんなことも知りませんでした。
自分で作ると柔らかさが自由自在に作ることができる!それも魅力ですね。
ほうとうを打つことになるなんて
もう一つのきっかけになったのは、
うちの子供が行っている小学校の行事(文化祭)で
「ほうとう作り」「柚子大根」
ということを行っていたんです。

その時のほうとう作りの
講師に近所のおばあちゃんたち
がきてくださっていました。
そのおばあちゃんたちはお嫁に来て
お姑さんにほうとう打ちを仕込まれたんだそうです。
80〜90代の方は打てますが
60代くらいから若い方は打てないとおっしゃってました。
昔の姑さんは厳しかったんですね^^;
この文化祭、地域と一緒になって文化祭を行うということが
新鮮で素晴らしいなと思いました。
私の娘もその時にほうとう打ちを教わって今でも打ち方を覚えています。
私も打てるようになりました。

↑ みんなそれぞれ個性あるほうとう(!)
残念ながら今はこの行事は無くなってしまったんですが、
この手仕事、ずっとやってきた技を伝えていかずにはいられない!と思いました。
手作り味噌作りをみんなで
あと、ご近所で共同作業として作る「味噌作り」。

みんなで作るのには意味があります。
たくさんの人の手を入れて常在菌を入れていくのです。
そうすることによって美味しい味噌になるそうですよ!
手作りたくあんが最高に美味しかった
「たくあん作り」は農家のお母さんとの出会いがあって教えていただきました。

大きな樽でたくさん漬けないと美味しくないよ、と
言われて生徒さんと共同でつけることにしました。
昔ながらの漬け方、天日に当てた大根で漬けていく、
乳酸菌いっぱいの漬物をいただける贅沢を
みんなでやってみたいと思ったのです。

梅干し手作りして15年

「梅干し」も疲労回復やサラサラ血液には毎日1個は食べたほうがいい。
本物の梅干しを食べるには、もう作るしかないですよね。
昔からの保存食作り、昔の台所は北側にあってしかも土間で、
底冷えを感じながら作業していたかもしれません。
実家の台所がまさにそうでした。
祖母が後ろ向きで後片付けをしていたり
母が、翌日の仕込みをしている後ろ姿。
とても心に焼きつていて、なんだか幼心に寂しく感じていました。
なので、大人になってカウンターキッチンというものを知って
とっても心が和んだのを覚えています。
「こんな素敵な台所があるんだー!」って。笑
そんな思いもあって
今の若いママたちはおもしろがって楽しんでやっていって欲しいと思っています。
楽しい「食」作り。
おもしろく深い、知恵の交換。
みんなでわいわいお話ししながら、いろんな情報交換にも貴重な場です。

またお子さんも一緒に参加してくださる方も多いです。
このような体験をさせてあげたいなあ、というのもあります。
今年はさらに色々なメニューを増やしていますので、
ご興味のある方は是非一緒に作りましょう!
今年の予定はこちらです。