自然豊かな田舎暮らしの中で、ドライトマトや手作りお茶など
「保存食 手作り」を楽しむ夏の手仕事を綴ります。
季節の恵みを活かした暮らしに興味がある方、
自給的な生活を目指す方へ。
実際にこんなことやってます!という体験をお話しします。
**************

発酵食品を手作り、田舎暮らしを実践している椿留美子です。
東京から家族で移住、のんびり・・と思いきや、全く忙しい!
全然スローライフじゃないよ〜、と思いながらあたふたしています。
田舎暮らしの知恵と奥深さをお伝えしたいと
東京と田舎を行ったり来たりしながら発酵教室を開催しています。
田舎暮らしの夏に欠かせない「保存食 手作り」という手仕事
お盆過ぎて朝夕の空気が変わってきました。
気持ちの良い気温でちょっと肌寒いと感じる日もあります。
最近は朝4時半くらいに起きるのですが、ちょうど朝日が昇ってくるという時刻。
それが、だんだんと遅くなってきています。
同じ時間に空をみると、季節の移り変わりがよくわかります。
最近の朝焼けです。

ここ数年の暑さは相変わらず尋常じゃないですね。
これからも残暑が続くでしょうが、それでも朝夕の過ごしやすさにホッとします。
今朝、ザクロが小さく実をつけていたのを見て、確実に秋が来ていることを感じました。
さて今日は、そんな今年の短い間の夏の「夏仕事」をご紹介します。
夏の台所には、季節ならではの手仕事があふれています。
とくに田舎暮らしでは、「保存食 手作り」は欠かせない暮らしの一部。
旬の恵みを活かし、冬に備える知恵と工夫がぎゅっと詰まっています。
私もこの夏、例年どおり「夏の手仕事」を楽しんでいます。
ドライトマトづくりに、おかき餅揚げ、そしてビワの葉茶。
バタバタと過ぎる日々の中でゆったりとした手仕事タイムは、
心を落ち着かせてくれる、ほっこりした時間です。
「夏の手仕事」とは?自然のリズムに合わせた暮らし

田舎で暮らすようになってから、季節ごとに変わる”台所仕事”が私の中で当たり前になりました。
春には山菜を採って塩漬けや佃煮に、秋には秋の味覚を加工する。
では夏は?
そう、トマトやお茶など、夏野菜や草木の恵みを保存する季節です。
暑さと湿気の中での作業は決して楽ではないけれど、
不思議と「忙しさの中にも心地よさ」がある。
手を動かしながら、自然のリズムと呼吸を合わせる感覚。
これこそが「手仕事」の醍醐味なのかもしれません。
梅雨明け後は梅の天日干し
まずは今年の梅雨明け一番は何と言ってもお待ちかねの
梅の天日干しです。
梅雨明けを待ってましたー!と周りも次々と干し始めていました。

今年は梅の生りがとてもよかったです。
発酵教室でもたくさん「梅干し」を仕込んでもらえました。
しかし自然のことは本当に予想を外れることがあります。
2020〜202年は梅の生育が悪くて、梅肉エキスの梅の確保も難しかったり、梅干しの梅の量も少ない年でした。
昨年2024年は成熟が早くて、追熟があっという間で梅肉エキスがうまくいかなかった・・・
ということがありました。
本当に自然は読めないことがあります。
今年のわが家の手仕事|ドライトマトづくり
さて、この夏はたくさんのミニトマトをいただきました。
(数年前から私の畑は手放したので、今はもっぱらいただく専門です笑)
食べきれない分は、さっそく「保存食 手作り」モードに突入です。
トマトは洗って半分に切り、ドライトマトへ。
作り方はこちらからどうぞ。
オーブンで作るドライトマトの作り方|ミニトマトの保存におすすめ!

ドライにすることによって甘みがぎゅっと凝縮されて手がとまりません^^
とはいえ、初めからうまくいったわけではなく…
実は、乾燥が甘いまま瓶に入れて常温で放置、カビを生やしてしまったことが(泣)。
それ以来、私は冷凍保存にしています。
半分はオイル漬けにして冷蔵庫へ。
パスタやピザ、サラダに入れると濃縮された甘みが口いっぱいに広がります。

これこそ「夏の手仕事」のご褒美です!
山の恵みでお茶づくり|枇杷の葉茶
薬草茶として今年はビワの葉茶を作りました。
作り方はこちらをごらんください。
動画で作り方を見たい方はこちら
ビワの葉には一般的に肌にいいと言われて、エキスを作ったり化粧水などお肌のケアに使われることが多いと思います。
ビワを使った療法は古くは奈良時代に中国から伝わってきたそうです。
ビワの葉を煎じることによって、皮膚炎や美肌効果も期待されました。
余分なものを排出したり、血液の浄化などいろいろな効果があるといわれて現代も重宝されています。
自然食品店などでも売られていますね。
薬草茶には、どくだみ茶や柿の葉茶などいろいろなものがあります。
どれもそれぞれに効果がある。
自然の力ってすごいです。
今年は、ご近所のお友達から葉っぱを譲ってもらって作りました。


香ばしくて飲みやすく、ノンカフェインなので夜でも安心。
素朴なおやつも「保存食」|揚げたて!おかき餅の手仕事
お盆までにそんな感じでいろいろと作りました。
そして、お盆にはお餅を作るおうちが多いです。
私の田舎(岡山)はお餅じゃなくてご先祖さんを迎える
「迎え団子」見送る「送り団子」というのを作っていました。
山梨はお餅をお供えして食べるそうです。
それも「信玄餅」!!さすが山梨です。
信玄餅をどう作るかっていうと、ついたお餅を伸して食べやすくカット。
それにきな粉と黒蜜をかけていただきます。
信玄餅だー!!
そんなお盆のお餅をたくさんいただいたので、食べきれないものをちいさくスライスして干しました。
おかき餅つくり

カラっからに干しておきます。
そして油で揚げるだけ。
とっても美味しいおやつの出来上がりです♡

ああ、こちらも手が止まりません(笑)
おやつでも、おつまみでも最高です!
ジュワッと膨らむ瞬間がたまらなく楽しく、揚げたてに塩をふるだけで、素朴で力強い味わいです。
「保存食 手作り」ならではの安心感と、手間をかける楽しさが、
おやつ時間をもっと豊かにしてくれます。
「保存食 手作り」でつながる、自然と暮らしと心
買わずにつくる。暮らしが変わる保存食の魅力
保存食を手作りしていると、自然と「あるもので工夫する力」が身についてきます。
うちはお菓子を買っていなかったので
娘なんかは「お菓子は作るもの」としていつの間には認識されていたようです。
食べたくなったら、夜遅くでも作り始めていました。
お店が近くにあるとすぐにスーパーで買えますが、この地域ではそうはいきません。
なので「家にあるもので何ができる?」と考えるようになりました。
経済的にも、精神的にも
あるものでなんとかする
感覚があります。笑
「夏の手仕事」を始めたい人へ|初心者が気をつけたいこと

ざっと夏の食仕事についてご紹介しました。
まだまだご紹介したいものがあるのですが、バタバタとしていて(いつもですが)
やりたいことが全部できるわけではありません。
その年のその期間にいくつかできればいい方です。
今年できなかったからまた来年・・・というふうにゆっくりです。
出来なくても全然平気。
最初は、いろいろやりたいのに出来ない(><)と焦っていたこともありますが、それだとつらくなるばかり。
プレッシャーにならないように「できなくてもいいや」と開き直るととってもらくになりました^^
ゆっくりやります。
保存食づくり初心者さんに伝えたいのは、無理をしないことです!!
まとめ|手仕事は、未来への贈りもの
季節の手仕事は、自然からの学び

手仕事を通じて学ぶのは、「自然のサイクル」と「自然に食べる」。
トマトが赤くなるのを待つこと。
葉が乾くまでじっと風を待つこと。
それは効率とは真逆にある、でもとても豊かな時間です。
子どもたちにも、こうした暮らしの知恵を伝えていけたらと思っています。
ゆったりと。美味しい夏仕事、おすすめです。
ご参考にしていただけたら嬉しいです。
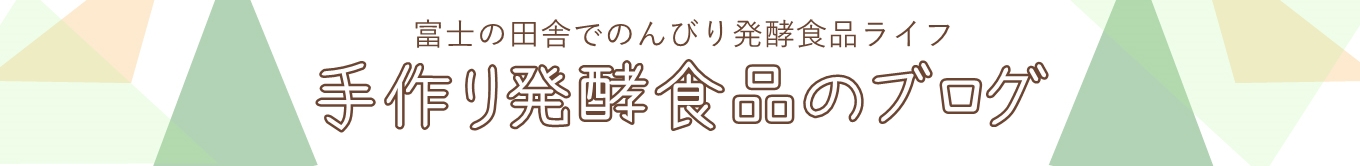

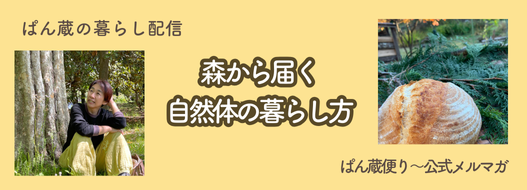


コメント