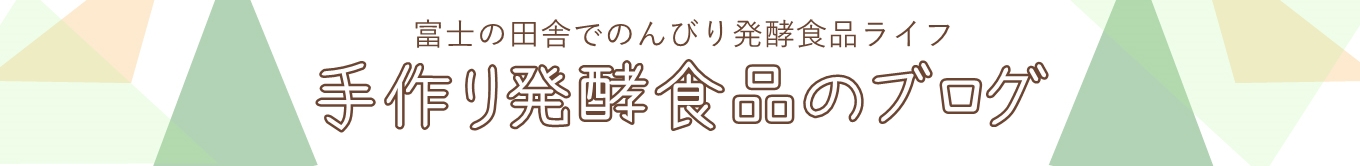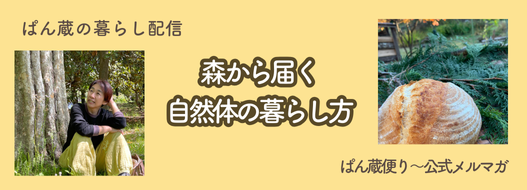私たちの生活の一部となっているお醤油作り。
田舎暮らしを始めてとてもいい出会いがありました。
それは調味料を手作りできること。
手作り醤油を始めて今年で10年目を迎えます。
今日はそんな醤油作りの「絞り」についてご紹介します。
**************

発酵食品を手作り、田舎暮らしを実践している椿留美子です。
東京から家族で移住、のんびり・・と思いきや、全く忙しい!
全然スローライフじゃないよ〜、と思いながらあたふたしています。
田舎暮らしの知恵と奥深さをお伝えしたいと
東京と田舎を行ったり来たりしながら発酵教室を開催しています。
手作り醤油 – 醤油絞りを迎える喜び2025
私たちのお醤油作り
そもそもお醤油なんて作れるの?って話です。
お醤油が自分たちの手で作れるなんて思ってもみませんでした。
専門家が醸造元で何年もかけて作るものだと思っていたからです。
それがこちらに移住してきて、
お醤油作りをしている方から
声をかけていただいたのがきっかけで始めることになり、
今や数人のグループになってそれぞれの地域でお醤油作りをやっています。

このお醤油の作り方は一般的なものとは違っています。
本物のお醤油は、通常は3年ほどかかると言われます。
しかしこのお醤油は1年かからずに作ることができます。
といっても一般に流通しているような工業的な作り方ではありません。
何回も天地返しして、数ヶ月かけて作っていきます。
なぜそんな短期間で自然に作ることができるようになったのか?
これは、このやり方を考えてくださった絞り師の方がいらしゃったからです。
以前、テレビのドキュメンタリーでその方の紹介もされていました。
とても珍しい方法なのです。
その方はお醤油作りをもっと身近に、主婦でも作れるというやり方で
地域のみんなと作るやり方を編み出してくださったのです。
この先代の知恵がなかったら、私たちは自分の手でお醤油を作ることなどできなかったでしょう。
本当に有り難い、嬉しいことです。
お醤油作りは仕込みから

お醤油作りは発酵食品です。
パンと同じく菌を入れて仕込みから始まります。
パンと違うのは作っていくスパンが圧倒的に長い(!)ということです。
1年かからないといっても数ヶ月かけて熟成させていきます。
大豆やお醤油麹の力です。
春に仕込みをして、夏を越し、そして冬〜春先にかけて絞ります。
どんなお味になっているか楽しみです。
毎年のことですが、ドキドキします。
その年の気候とか保存状態によって味が違ってくるんですよ。
毎年、「今年はうまくいったかな・・・」と緊張するわけです。
だいたい12月〜3月に絞ります。
さて、今年のもろみはどんな感じでしょうか。
お醤油作りの仲間になって、今年で10年目になりますが
毎回ドキドキわくわく。
今回は、どんな様子でお醤油絞りをしているのかご紹介していきたいと思います。
お醤油絞りの様子
今年の絞りは雨が降って写真がうまく撮れなかったので
こちらは以前のお醤油絞りの様子です。
↓

朝7時から薪でお湯を沸かし始めます。

長野から絞り師さんがきてくださいました。
「ふね」と呼ばれるお醤油の絞り器(?)を組み立てていきます。

沸いたお湯をもろみに足して行きます。
ここが絞り師さんの腕ありきなんです。
素人には難しい。
適度に調整しつつ、お湯を足して絞り袋に入れていきます。
もろみの入った袋をふねに入れます。
そうして圧縮してお醤油が出てくるんです。
ポトポト落ちてきました。

今年のお醤油のできはどうかな??
と、ここでみんな味見をします。
これがお楽しみの時間です。
「美味しいー!!」
と子供もペロペロ舐めちゃいます。
絞ったお醤油を今度は火入れして、アクをとり冷まして出来上がりです。
こうやって1日がかりでみんなで協力してやっていきます。

お醤油作りから考える〜トータルでできるということ
自分たちの口に入れるものは自分たちで作る。
昔は当たり前になっていたことが今は分業制になっています。
「作る人」
「配送する人」
「売る人」
「買う人」
「食べる人」
そういう仕組みでものすごく便利な世の中になりました。
そうなると出来ることと出来ないことの差が大きくなるのも確かです。
一つのところでトータルにやっているとみんなマルチにいろんなことを知っていて
技術も身についている。
それが専門色が強くなって出来ないことが多くなるんですね。
そしてどんどん顔が見えなくなってくる。
どんな人がどんな感じで、どんな思いで作業しているのか。
それを一つのところでやりたいと集まったのがこのメンバーです。
よくばり仲間です^^
そしてこの私たち普通の主婦でも出来るお醤油の作り方を
考え出してくれた方がいらっしゃいます。
その巨匠はもう亡くなってしまいましたが、
それを受け継いでいる絞り師さんが何人もいらっしゃいます。
ありがたいです。
やっぱり自分たちで作ったものは美味しい!
材料も何を使っているのかはっきりしている。
どんな手間をかけたのかも知っている。
何より愛着がある。
大事に使うし、苦労したから「ありがとう」の気持ちで毎回食べます。
絞りが終わった後のご飯も美味しい!!
絞りたてのお醤油を使ってご飯をいただきます。
今回の持ち寄りご飯もモリモリでぜいたくー!
熱々のご飯、卵の上にお醤油をかけていただくのもサイコー!

みんなの持ち寄ったおかずでちょっとしたパーティです。
お楽しみのご飯の時間^^


こんなふうにして、一つのことを協力して作り上げていきます。
いつもと変わらない日常とは
まさに絞り師の先生がおっしゃっている
「村仕事」なのです。
地域の人たちで何かを一緒に作る。
こんな交流が今でもできていることに感謝です。
2020年に新型コロナウィルスの流行という
世界的規模の脅威が起こりましたが、
その時も、田舎の「村仕事」では全く何事もなかったかのように
いつもと同じように行われていきました。
いつもと変わらない日常
さりげなく、何気なく身近にあるので忘れてしまいがちですが
これが何よりの幸せなんですね。

そんな日常を愛おしく大切にして生きていきたい。
このお醤油を作るときそんなことを思います。
さあ、このあとはお醤油の瓶詰め作業が待っています。
瓶に詰めてやっと我が家に持ち帰れるのです。
楽しみだなあ〜。