発酵食品というと何を思い受かべますか?
味噌、ヨーグルト?
数年前からの発酵食ブームもあって手作りされている方も増えましたね。
ヨーグルトメーカーを持っている方もたくさんいらっしゃるのにはびっくりしました。
今日はそんな発酵食品を作るにあたって、
大切なポイントをお話ししてみたいと思います。
**************

発酵食品を手作り、田舎暮らしを実践している椿留美子です。
東京から家族で移住、のんびり・・と思いきや、全く忙しい!
全然スローライフじゃないよ〜、と思いながらあたふたしています。
田舎暮らしの知恵と奥深さをお伝えしたいと
東京と田舎を行ったり来たりしながら発酵教室を開催しています。
発酵食品は身体にいいの?
数年前の震災、近年の自然災害やウィルスの蔓延などで
私たちの生活を脅かすような出来事が次々と現れていますね。
そんな時、振り返るのが
「それに耐えうる身体作り」
です。
身体作りといえば食生活がとても重要な要素になってきますね。
そんなこともあってか、発酵食品が注目されるようになってきました。
「発酵食品を食べよう」と近年よく聞くようになった?
そうかもしれませんが、実は第二次世界大戦後にも実績を残しています。
長崎の爆心地よりたった1.4kmのところにある病院で
被曝された秋月医師は
味噌汁、玄米、梅干し中心の食事を進め、
それに従った職員に原爆症が出ることはなかったそうです。
多くの方が原爆症で亡くなる中、自ら被曝したにもかかわらず患者の治療に
奮闘されたのはこの「味噌汁」食事療法のおかげだったと言います。

その後、広島大学の研究所で科学的に証明されました。
すごいことですね。
私たち日本人の昔ながらの食事にはちゃんと身体を支えてくれる力があるのです。
味噌、醤油、漬物などの発酵食品は和食の基本となるところですね。
私も今やっている講座で中心にしたいと思ったのが
味噌
梅干し
たくあん
という昔ながらの保存食です。
まさしく秋月先生の食事法!だったと嬉しく思いました。
日本人は昔から発酵食に囲まれた生活を送ってきていたんです。
それが現代は外国の食材や調理法などいろいろなものが
手軽に楽しめるようになっていて
ちょっと和食の頻度が減ってきているような印象です。
楽しいことだとも思いますが、
今一度発酵食が見直されているというのは
私たちのDNA に発酵文化が刻まれているからかもしれませんね。
発酵食品 手作りの魅力とは?

市販品では味わえない“生きた味”
発酵食品は本来発酵し続けるものですが、
市販されているものは品質安定のために
ほとんどが熱処理などをして発酵しないように処置しています。
私の自家製酵母レッスンでは「ビール酵母」を扱うものがありますが
これも生きているビールじゃないと作れません。
市販のものは多くは酵母菌を取り除かれています。
菌がいるとどんどん味が変化していくので困りますよね。
手作りで味の変化を楽しむのは醍醐味ですが、売っているものが変化して
「この前と味が違う!」とクレームがきたら大変です。
本当に発酵しているものを口に入れるのは、
もはや手作りのものしかない・・時代かもしれませんね。
自分で作ると乳酸菌や酵母が元気なまま味わえます。
発酵中の香り、酸味や甘みの変化を感じられるのも手作りならではですね。
腸活・免疫力アップへの効果
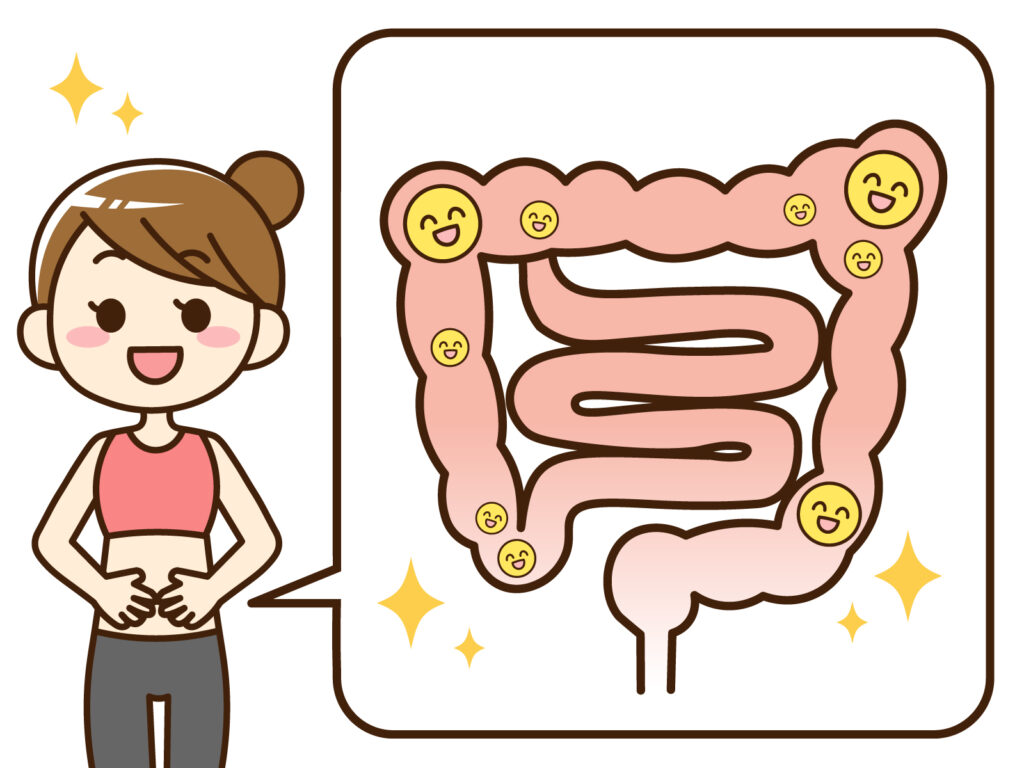
発酵食品には乳酸菌や酵母が豊富に含まれ、腸内環境を整える効果があります。
私自身、発酵食品を毎日の食卓に取り入れるようになってから、
風邪をひきにくくなり、なんと言っても「冷え」が改善されました!
発酵調味料 自家製で暮らしが楽しく
塩麹・醤油麹・甘酒は意外と簡単
塩麹は塩と米麹と水を混ぜて常温で1週間ほど。
醤油麹は醤油と麹を合わせて数日。
甘酒は炊飯器やヨーグルトメーカーを使えば一晩で完成。
忙しい人でも取り入れやすい発酵調味料です。
料理の味がワンランク上がる使い方
塩麹は肉や魚の下味に、
醤油麹は炒め物や煮物に、
甘酒は砂糖代わりにスイーツやドレッシングに使えます。
塩麹でマリネした鶏むね肉をオーブンで焼くだけで、
家族から「今日はごちそうだね!」と言われますよ!
保存期間と保存方法のコツ
塩分濃度が高い塩麹や醤油麹は冷蔵で数か月持ちます。
甘酒は冷蔵で1週間ほど。
長期保存したい場合は冷凍がおすすめ。
作り置きしておくと、毎日の料理がぐっと楽になります。
私の発酵生活体験談|初めてのパン・味噌・漬物作り
天然酵母パン作りで感じた発酵の力

初めてレーズン酵母を起こしたとき、瓶の中でぷくぷくと泡立ち、
香りが変化していく様子に感動しました。
その酵母で焼いたパンは、市販のイーストでは出せない優しい香りと深い味わい。
噛み締めるほどに美味しい、とはこのことか!と思いました。
味噌作りで知った手間と愛情

冬の寒い日に、大豆をふっくら煮て、麹と塩を混ぜて樽に仕込む。
出来上がるのは約一年後。
その待つ時間こそが味噌作りの醍醐味。
蓋を開けたとき、カビにドキドキするのもまた楽しみであり恐怖(?)でもある笑
味噌作りについてはこちらもご参考にしてください。
手作り味噌はなぜ美味しい?田舎の知恵と常在菌の秘密|講座で広がる発酵の世界
漬物は“放っておくだけ”でも奥が深い

漬物作りも楽しいです。
塩を振っておくだけで水が上がってきて、酸味が出て旨味が増すのです。
塩ってすごい!
と感動します。
ぬかの力を借りれば「たくあん作り」も美味ですね。
どれも植物性の乳酸菌の活躍ですね。
初心者でも失敗しない!発酵食品 美味しく作るコツ
刺激を与えるってどういうこと?美味しくなるコツ
さて、そんな発酵食品ですが、
「刺激を与える」
ということが重要なポイントになってきます。
このお話を動画でご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
本来の発酵食品とは菌が生きている食品です。
菌が生きていて発酵し続けているもの ということですね。
味噌、漬物、ヨーグルトなど。
本来は発酵し続けているので日ごとに状態が変わっていくのが普通です。
私たちが地域の仲間で作っているお醤油は置いておくと蓋が飛びます(笑)
発酵が進んでガスが溜まってくる勢いで蓋が外れるんです。
ポンっといきなり音がしてびっくりします。
さて、この「発酵」ということが作っていく工程に入っているものは、
手を入れてあげる、ということが重要になってきます。
刺激を与えてあげることによって活性化していくのです。
今、私が作っているものだと味噌、たくあんなど
発酵クラスのレッスンでやっているものがあります。
漬物類だとぬか床もそうですね。
お醤油も発酵させて熟成させていきます。

そのどれをとっても共通点があってすべてに刺激を与えます。
どういうことかというと、
味噌、醤油=天地返し
ぬか床=混ぜ返し
パン=パンチ(ガス抜き)
天然・自家製酵母=混ぜ返し
ということになります。
これは空気を含ませていくということです。
酸素を取り入れることによって酵母の活性化につながり、
より強く、より発酵力が高まっていくのです。
お醤油は昔ながらの作り方では、ずっと混ぜ続けているということですよ。
私たちが地元で作っているやり方はちょっと特別でずっと混ぜなくてもいい、
極力手間を省いた地域のお醤油作り
(これを開発してくださった方がいらっしゃいます!)
をやっていますが
それでも仕込んだ最初のころは乳酸発酵を促すために頻繁に天地返しをやります。
そうすることによってとてもいい状態になっていきます。
味噌もそうですね。
1~2月頃仕込んで梅雨明けに天地返しをします。

味噌に手を入れて容器の底から混ぜ返していきます。
(最近は天地返ししないで冷暗所で1年くらい置いておく、というやり方も聞きます)
実は、ぱん蔵のレッスンでやっている味噌は天地返ししません。
これは良質な麹と麹の量の関係で天地返し不要ということになっていますが、
もちろんやっていただいてもいいのです。
そのことによって発酵が早く進んでいい状態になっていきます。
手を入れて混ぜ返すといえば酵素ジュースもそうですね。
これもヘラなどの道具を使わず、わざと手を使って混ぜていきます。
手についている菌、常在菌を入れていくということが大切だと言われています。
とにかく発酵を促すためには混ぜ返して空気を含ませてあげる
ということが大事になってきます。
(そんなに刺激を与えないで静かに発酵させていくものもあります)
パンを作る時、何か発酵食品を作る時思い出していただくといいと思います。
発酵生活を続けるための工夫と楽しみ
私たちの身近に実践できるところでは麹を使った調味料があります。
塩麹
甘酒
醤油麹
麹はスーパーなどでも簡単に手に入りますので、それを使って混ぜ込んでおくだけ。
甘酒は温度管理が重要になってきますが、コツをつかめば簡単に作れます。
とっても簡単で美味しいのでおすすめです。

と言っても、最初はうまく作れるか?不安だったり
やっぱり面倒くさいかも・・・
とかで、作るのにためらわれることもあるでしょう。
そんな時には市販のものからお試しください!
まずはできているものを買ってみて、試してみる。
「こんな風に使うんだ!」
ということがわかれば、日常に取り入れやすくなります。
そこからスタートしてもいいのです ^ ^
手作りじゃないと・・・
と思わず、最初はお手軽に始めることをお勧めします!
まずは気軽に試して、ちょっとずつ取り入れてみてくださいね。

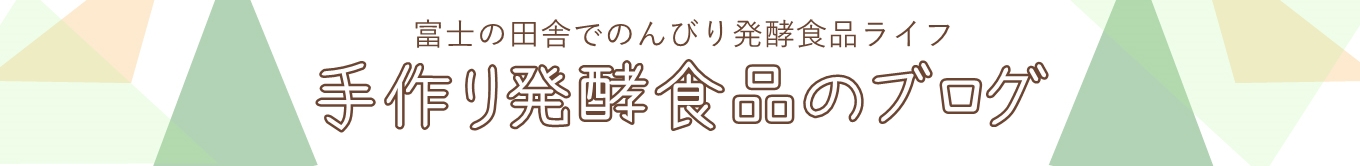

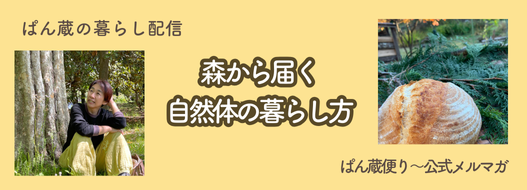


コメント