手作り味噌や保存中の味噌に
カビが生えたらどうしますか?
慣れていないと驚いてしまう方もいらっしゃるでしょう。
今回は、白い産膜酵母との違いや安全な見分け方、
私の味噌作り失敗談から学んだ対処法・予防のコツを解説していきます!
**************

発酵食品を手作り、田舎暮らしを実践している椿留美子です。
東京から家族で移住、のんびり・・と思いきや、全く忙しい!
全然スローライフじゃないよ〜、と思いながらあたふたしています。
田舎暮らしの知恵と奥深さをお伝えしたいと
東京と田舎を行ったり来たりしながら発酵教室を開催しています。
味噌にカビが生える原因と種類

手作り味噌や保存中の味噌を開けたら、
「あれ?表面が白い…」
そんな経験はありませんか?
味噌は生きている発酵食品。
熟成中にカビが発生することもあります。
では、どんなカビがあり、どう見分けたら良いのでしょうか?
色でわかるカビの特徴
まず、味噌に生えるカビには3種類あります。
色でいうと、白、黒、青 です。
白いカビは産膜酵母?
白い薄い膜のようなものは、必ずしも危険ではありません。
その正体は「産膜酵母(さんまくこうぼ)」と呼ばれる酵母菌の一種で、
多くの場合は人体に害はありません。
黒・青は要注意!
一方で、黒カビ・青カビは有害の可能性があります。
○黒カビはカビのように見えて表面が酸化して黒ずんでいる場合が多いです。
青カビが黒っぽく見える場合もあります。
○青カビはいわゆるよく見かけるアオカビです。
人体に良くない影響を与える可能性があるので、見つけたらすぐに取り除いた方がいいです。
私が初めて味噌作りでカビに出会った日

初めて味噌を仕込んだ年、本を見ながら自己流で挑戦しました。
梅雨明けに天地返しをするため蓋を開けた瞬間、
そこにはカビの世界が…!
恐怖でおののきました (@@)!!
しかし、表面のカビを取り除いてみると、
その下には美しい味噌が広がっていました。
その光景はまるで『風の谷のナウシカ』(ジブリでお馴染み)
の腐海の下のきれいな空気のようで、
「カビが守ってくれていたのかもしれない」
と感じた瞬間でした。

カビを見かけたら、最初はびっくりすると思います。
味噌を作り始めてまだ慣れていない方は、「味噌容器の蓋を開けるのが怖い」(><)とおっしゃいます。
私もそうでした(笑)
でも、生えるなんて当たり前~、と思ってドンと構えてください。
産膜酵母とは?食べても大丈夫?
産膜酵母は発酵過程で酸素に触れる表面に発生する酵母の一種です。
空気に触れている部分に発生し、耐塩性という特徴があるので味噌やお醤油によく現れます。
「昔のお醤油はよく白いカビが発生していた」
という話を聞いたことがあります(カビじゃないですが)。
確かにうちで作るお醤油も
そのまま放っておくと空気に触れている部分が白くなってきます。

先ほども「色でわかるカビの特徴」のところでお話ししましたが
多くの場合は健康被害はありません。
味噌と醤油での発生例
私は地域の仲間と醤油作りを10年以上続けていますが
初めて醤油の表面に白い膜が現れたときは正直焦りました。
他のグループではよく聞く現象でしたが、私たちのグループでは初めての経験。

慌てて絞り師さんに相談すると
「それは産膜酵母だから心配ありません」と教えてもらい、
安心して適切に処置することができました。
味噌にカビが生えたときの正しい対処法
安全に取り除く方法
- カビが生えた部分より少し広めにスプーンやヘラで削り取る
- 周囲の味噌も念のため数ミリ削る
- 容器の縁や蓋もアルコールで消毒
混ぜ込んではいけない理由
私もかつて「産膜酵母だから大丈夫」と思い、
白いものを味噌に混ぜ込んだことがあります。
結果…味が落ち、せっかくの味噌が残念な風味に(泣)。
それ以来、必ずきれいに取り除くようにしています。
絶対に食べない方がいいケース
- 青・黒カビが発生している
- カビ臭や異臭が強い
- 味噌全体の色や質感が大きく変わっている
味噌作りでカビを防ぐ予防のコツ
容器・保存場所の選び方
- きれいに洗い、しっかり乾燥させた容器を使う
- 直射日光を避け、温度変化の少ない場所で保存
塩とラップで予防率アップ

表面に塩を薄くまぶし、空気に触れないようラップで覆うとカビの発生を抑えられます。
重しの代わりに塩で重しをしてもいいですね。
まとめ:カビは発酵の一部として受け止めよう
味噌や醤油を通して感じたのは、
カビや産膜酵母は現れるのが「当然」と思っておくくらいの方がいい!ということです。
慌てることはありません。
適切に対処すれば十分食べられます。(慌てて捨てないでね)
表面を覆うそれらは、下にある美しい発酵食品を守ってくれている場合もあります。
もちろん安全な範囲での話ですが、失敗やトラブルも含めて発酵の世界は奥深く、
自然の神秘を感じさせてくれます。
カビが出ても落ち込まず、学びの機会として受け止めてみましょう。
発酵暮らしをもっと楽しみたい方は、ぜひ私のメルマガに登録してみてください!
色々な体験を共有しています ^ ^
👉 📩 メルマガ登録はこちら
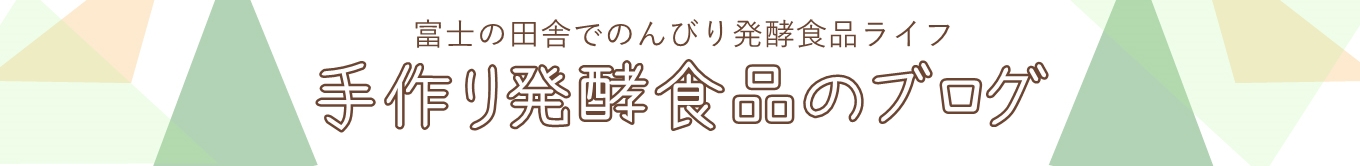

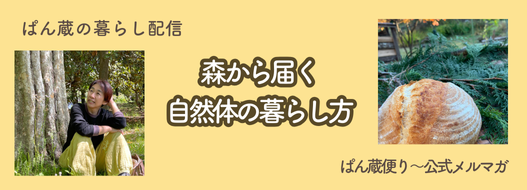
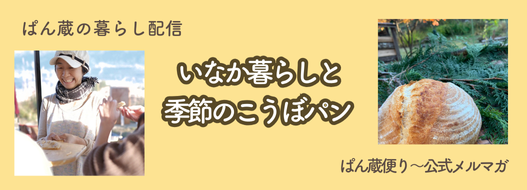


コメント